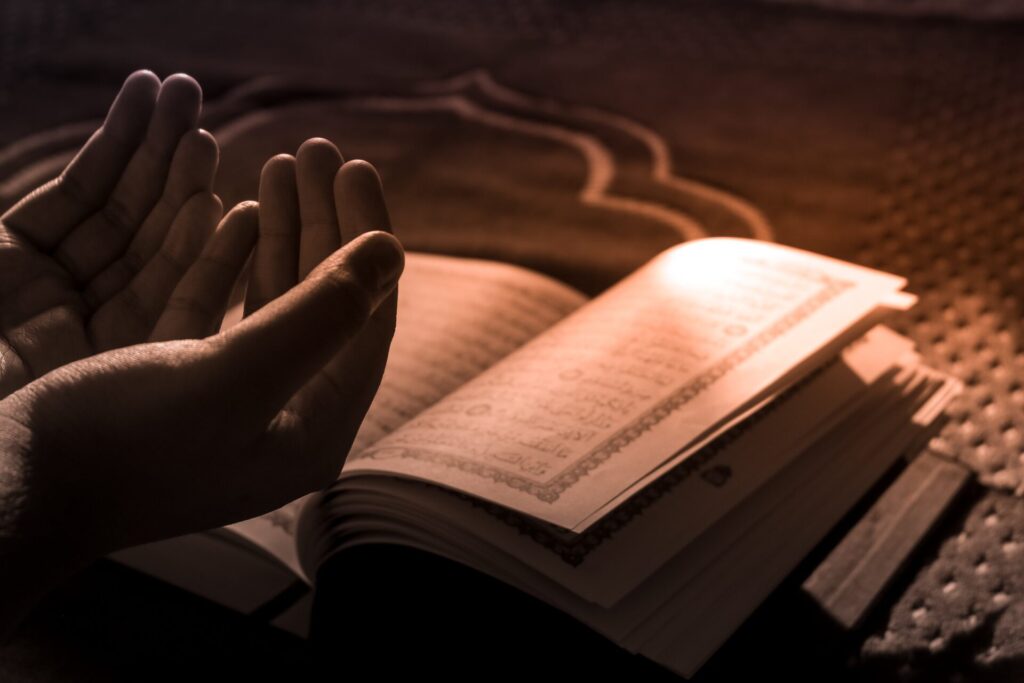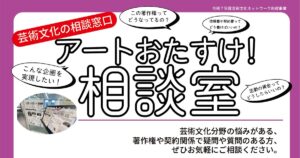「作者が伝えたかったことを書きなさい?なもん知るかよ!原稿料まだかなーって思ってるかもしれんし、今日の晩御飯は何だろうなって思ってるかもしれないだろ。でもお上からはこう教えろって言われてるんでね」
高校時代の国語の先生はこう言いました。
「ここで言う問題は、作者が何を言いたいかじゃなくて、問題を作った人が『こういう風に答えてほしい』という意図に忖度することなんだよ」という本質を学ぶことができました。
それから国語や文章問題は得意になりました。
いわば、行政書士試験の問題もこのスキルが非常に重要になります。
足切りのある基礎知識問題では、高校レベルの文章理解問題は3問とも取りたいところですし、多くの受験生が苦労している記述問題も、あなたが考えていることではなく、「出題者が答えてほしい通りの答えを書く」ことが重要です。
また、文章を早く読み理解する能力は、それだけ同じ時間でより多くの問題を解くことができるようになります。
表現における本音と建前
例えば、日本語の慣用句(決まり文句)は以下のようなものがあります。
「お疲れ様です」→ 挨拶(実際に疲れているかは関係ない)
「いらっしゃいませ」→ 歓迎の定型句
「失礼します」→ 退室時の決まり文句
英語だとこのような感じですね。
“Good morning” → 朝の定型挨拶(天気や気分に関係なく)
“How are you?” → 本当に体調を聞いているわけではない
“Have a nice day!” → 社交辞令(相手の一日を本当に心配しているわけではない)
このように本音と建前を両方教えてくれる先生がいたら自分は英語にもっと興味を持てたのかもしれない。
逆に、「日本人はなんでいつも疲れてるの?」と誤解する外国の方もいらっしゃるかもしれません。
勉強というのは本音と建前の両方を学んでこそ真に身に着くものだなと最近、とみに感じます。
教育における本音と建前
ですが、現在の学校教育では「本音」を教えることは大変難しいと思います。
大量のカリキュラムの中で教師の裁量も限られています。
私は私立の高校に通っていましたので、公立となると更に顕著になるのでしょう。
現代では漢字が書けなくても、少なくとも読み方が分かっていれば支障が無いことが多いです。
私たち行政書士も、字が綺麗に書けることよりもパソコンやインターネットなどデジタル社会に精通した存在であることを求められています(「書士」という通り、これまでは紙の書面だったものが、急速にオンライン上で手続きするように変わっています)。
しかし、長文を素早く読み、その意図を見抜くスキルというのはどのような形にも活かすことができます。
最近はAIによる要約機能もありますが、解釈の違いや、隠された意図や建前、皮肉のようなものを読み取るのは難しいでしょうから、それに頼り切るのは危険です。
さいごに
色々な制約の中で、実直に、本音を持って教えて頂いた先生のおかげで私は国語という教科が好きになり、行政書士の試験も合格することができました。
先生にこの場をお借りしてお礼申し上げます。