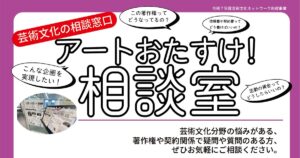フリーランス新法とは?
こうしたトラブル、フリーランスとして活動する方なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。あるいは、実際に経験された方もいらっしゃるかもしれません。
音楽制作、デザイン、イラスト、ライティングなど、クリエイティブな仕事をする多くの方が、個人事業主(フリーランス)として活動しています。しかし、企業や団体と比べて立場が弱く、不利な条件を押し付けられたり、報酬トラブルに巻き込まれたりすることが少なくありませんでした。
そんなフリーランスの人たちを守るために、令和6年11月1日に「フリーランス新法」が施行されました。
正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
この記事では、フリーランス新法の基本と「誰が保護されるのか」について、長浜市でクリエイター支援を行う行政書士が分かりやすく解説します。
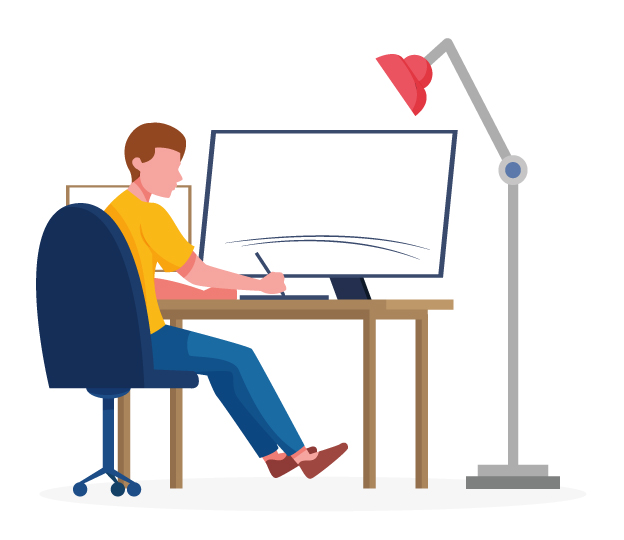
フリーランス新法の成立の経緯
民法では、「契約自由の原則」というルールがあります。これは、人と人との間では法令に反しない限り、原則としてどのような契約を結んでも構わないというものです。
また、契約の成立には書面の作成などは必要ありません。口約束でも、当事者の間で合意していれば契約は成立します。一見、自由で便利なルールに思えますが、ここに大きな問題がありました。
フリーランス(個人事業主)は企業や自治体などに対して一般的に立場が弱く、不利な契約を締結させられたり、報酬の未払いなどのトラブルが多く発生していました。
特にクリエイターの場合、「好きなことを仕事にしているんだから」という理由で、不当に安い報酬や無理な条件を押し付けられることもありました。
こうした状況を改善し、フリーランスの立場を保護する目的として、フリーランス新法が令和6年11月に施行されました。
この法律により、発注者(企業や団体)には様々な義務が課され、違反した場合には行政指導や罰則の対象となります。

フリーランスの定義
フリーランス新法で保護される対象は、すべてのフリーランスではありません。この法律では、保護されるフリーランスを「特定受託事業者」と呼んでいます。
特定受託事業者の定義
以下のいずれかに該当する人が「特定受託事業者」です。
・個人で、従業員を使用しない
・法人で、代表者以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用しない
※従業員 = 週の所定労働時間が20時間以上、かつ勤務開始時から31日以上の雇用が見込まれる者
役員 = 理事・取締役・監査役など
重要なポイント
①1人会社も特定受託事業者として扱う
法人化していても、代表者1人だけで従業員を雇っていない場合は、フリーランス新法の保護対象になります。
②副業フリーランスも保護される
企業に会社員として勤務しながら、副業としてフリーランスの仕事を行っている場合も適用されます。
例:
・平日は会社員、週末に音楽制作の仕事を受けているミュージシャン
・本業の傍ら、夜間にイラストの仕事を受けているイラストレーター
③家族の手伝いや短期アルバイトは従業員に該当しない
・仕事を手伝っている家族(生計を一にする親族)
・週20時間未満のパート・アルバイト
・業務委託の再委託先(外注先)
これらは「従業員」に該当しないため、上記の人を使っていても特定受託事業者として認められます。

業務委託事業者の定義
次に、発注者側の定義を見ていきましょう。フリーランス新法では、フリーランスに業務委託を行う発注者を2種類に分けています。1つ目が「業務委託事業者」です。
業務委託事業者の定義
実は、特定受託事業者(フリーランス)と要件は同じです。
・個人で、従業員を使用しない
・法人で、代表者以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用しない
業務委託事業者に課される規制
業務委託事業者は、以下の義務を負います。
①書面等による取引条件の明示義務
この義務については、第2回の記事で詳しく解説します。簡単に言うと、「契約内容を書面やメールで明確に示さなければならない」というルールです。
重要なポイント
・フリーランスがフリーランスに発注する際に適用される
例えば、デザイナーAさんがイラストレーターBさんにイラスト制作を依頼する場合、Aさんも「業務委託事業者」として書面等の明示義務を負います。
「自分もフリーランスだから関係ない」ではなく、発注者側になったときは義務を守る必要があります。
・家族や一般消費者は業務委託事業者に該当しない
事業として行っておらず、趣味として依頼した者などは業務委託事業者に該当しません。
例:従業員10人を雇用する運送業の社長Aが、自宅の庭のガーデニングをフリーランスの造園家Bに依頼した場合、社長Aの本業とは関係がない個人的な依頼のため、Aは業務委託事業者とは扱われず、フリーランス新法は適用されません。

特定業務委託事業者の定義
発注者側の2つ目の分類が「特定業務委託事業者」です。こちらはより多くの義務が課されます。
特定業務委託事業者の定義
業務委託事業者とは異なり、従業員を雇っているか、役員がいる事業者を指します。
・個人で、従業員を使用している
・法人で、代表者以外に他の役員がいる、または従業員を使用している
規制の対象
①書面等による取引条件の明示(第2回で解説)
②報酬の支払いに関するルール
③報酬の減額や買いたたきなどを禁止する7つの事項
④広告等の募集情報の的確な表示
⑤契約の中途解除等の事前予告
⑥妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
⑦ハラスメントに対する防止措置の整備
業務委託事業者が①のみの義務を負うのに対し、特定業務委託事業者は①〜⑦のすべての義務を負います。
重要なポイント
・NPO法人や市町村は原則として特定業務委託事業者
この条件により、NPO法人や学校法人、市町村などの行政法人がフリーランスに業務委託を行う場合は、原則として常に特定業務委託事業者になります。
代表以外の役員がいるか、従業員を使用しているか、いずれかの要件を必ず満たすためです。
(細かい話をすると、一般社団法人は代表理事一人でも活動できるため、特定業務委託事業者にならない場合があります)
・企業の規模は関係ない
従業員が1人でもいれば、特定業務委託事業者になります。大企業だけでなく、小規模な会社でも同じ義務を負います。

まとめ
フリーランス新法は、個人事業主や1人会社として働くクリエイターを守るための法律です。
✅ フリーランス新法は令和6年11月1日から施行
✅ 保護される「特定受託事業者」=従業員を雇っていない個人・1人会社
✅ 副業フリーランスも保護の対象
✅ 発注者は「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に分類
✅ フリーランスがフリーランスに発注する場合も義務がある
✅ 企業の規模に関わらず、従業員がいれば「特定業務委託事業者」
フリーランスで働く方は、まずは自分が「特定受託事業者」に該当するかを確認しましょう。該当する場合は、この法律によって様々な権利が保障されています。
また、自分が発注者側になる場合(他のフリーランスに仕事を依頼する場合)も、義務を守る必要があることを覚えておいてください。
次回の内容
次回(第2回)は、「①書面等による取引条件の明示義務」について詳しく解説します。
・口約束で仕事を受けるのは危険?
・「直ちに」書面が必要とは?
・LINEでのやり取りは契約書として有効?
・契約書に必ず書くべき項目とは?
フリーランス新法で最も基本的で重要なルールについて、実践的な内容をお届けします。