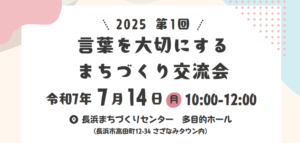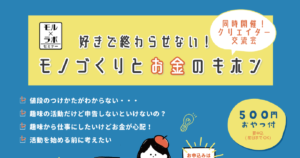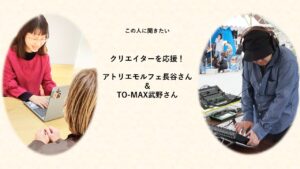はじめに
行政書士として地域の皆様のお手伝いをさせていただく中で、日々感じることがあります。それは、真に多様性を受け入れる社会の実現がいかに重要かということです。今回は、一見些細に思える「酒を飲む・飲まない」という話題を通じて、私たち専門家が目指すべき姿勢について考えてみたいと思います。
体質の違いを人格の問題にしてはいけない
私自身、体質的にアルコールを受け付けません。これは花粉症や乳糖不耐症と同じ、単なる体質の問題です。
しかし長年、「付き合いが悪い」「真面目すぎる」といった人格的な評価をされることがありましたし、会社員時代の飲み会は苦痛以外の何物でもありませんでした。
行政書士として独立した後、様々な立場の方々とお仕事をさせていただく立場から強く感じるのは、酒を飲まないくらいで文句を言われるような社会では、到底、本当に困っている人が救われることはないということです。
有難いことに私は花粉に耐性がありますが、花粉症で悩む人に「気合の問題だ」と言えば明らかにおかしいことは明白です。私たちが、このような小さな違いさえ受け入れられないとしたら、身体的な制約を抱える方、文化的背景の異なる方、経済的困窮にある方など、より深刻な状況にある方々をどうして支援できるでしょうか。

多様なコミュニケーション スタイルの価値
「酒が飲めなければ仕事につながらない」という風潮が現在も一部存在することは認識しています。しかし、私が行政書士として開業してからの経験では全くそのようなことはありません。
例えば、
・女性のクライアント様の場合、同性か気の知れた友人と飲みに行くことが多いので、私が仕事をする上でお酒を飲まないことのデメリットはほとんどない
・高校生バンドのメンバーと協業する音楽ワークショップでは、音楽という共通言語で世代間のコミュニケーションが取れているが、未成年なのでそもそもお酒の付き合いが存在しない
・地域の高齢者の方々との関わりでも、地域によりますが、自分の自治会ではお酒の席を強制されることはありません(古い価値観をアップデートしなければと感じている方も多い)

なぜ人は他人に酒を勧めたがるのか
心理学的に考えると、他人に飲酒を強要したがる人の心理には「認知的不協和」が働いていることが多いものです。つまり、自分の飲酒習慣に対する後悔や不安を、「自分は間違っていない(いなかった)」と正当化しようとしているのです。
本当に心からお酒を楽しんでいる方は、他人に強要したりしません。酒が好きな人同士で楽しめば、それで十分なのです。
専門家に求められる本当の資質
行政書士をはじめとする士業の専門家に求められるのは、酒席を盛り上げたり面白いことを言ったりするようなものではありません。
これらの能力は、酒の席よりもむしろ、冷静で集中できる環境でこそ発揮されるものです。
時代の変化とチャンス
コロナ禍以降、社会全体で働き方や人間関係のあり方が見直されています。オンライン会議の普及、ワークライフバランスの重視、そして多様性への理解の深まり。これらの変化は、従来の酒文化に馴染めなかった方々にとって大きなチャンスでもありました。
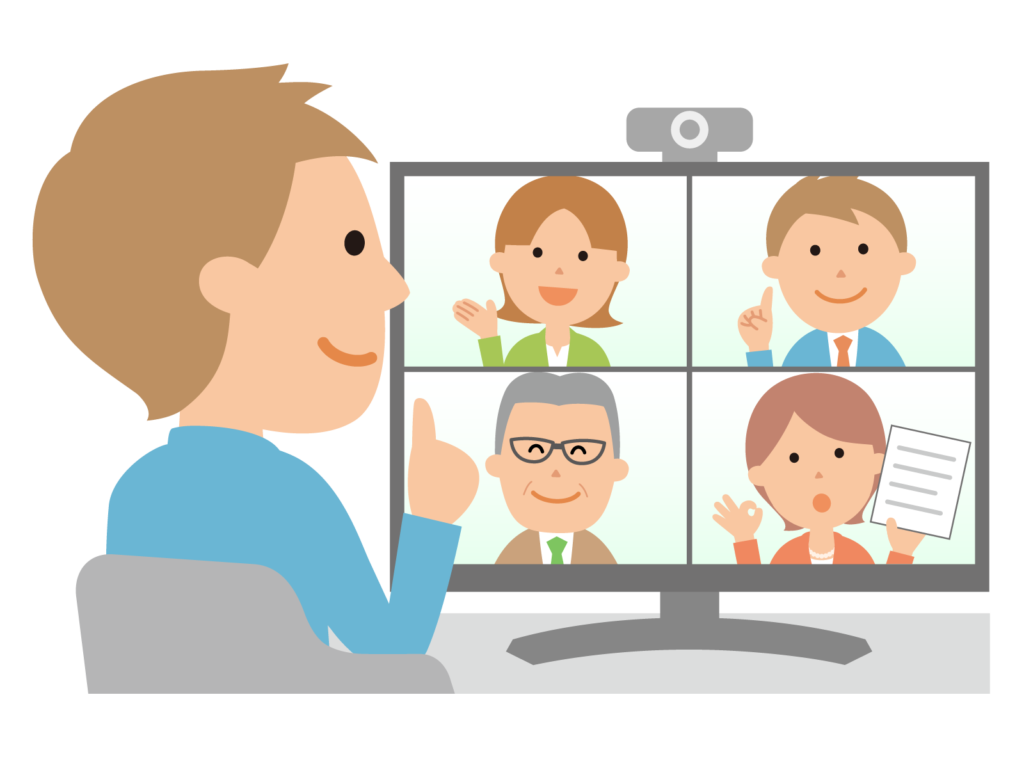
おわりに
私は長浜市において、地域密着型の行政書士として活動させていただいています。酒は一滴も飲めませんが、それが業務に支障をきたしたことは一度もありません。むしろ、様々な制約や困難を抱えた方々の気持ちに寄り添えるようになったと感じています。
真の専門家とは、表面的な付き合いではなく、実質的な問題解決によって信頼を築く人間のことです。体質や価値観の違いを理由に排除されることのない、本当の意味で多様性を尊重する社会の実現に、専門家として貢献していきたいと考えています。
どのような背景をお持ちの方でも、安心してご相談いただける事務所を目指して、日々研鑽を積んでまいります。