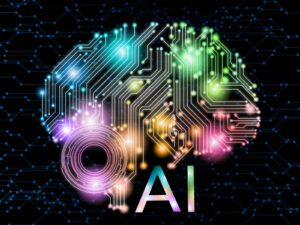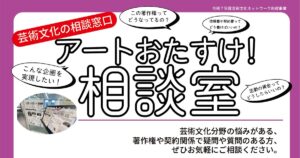行政書士はAIに仕事を奪われるのか?
手続きの複雑さ
私は行政書士と宅建の登録を並行して手続きした経験から、手続きの複雑さを痛感しました。
この場合は厳密に言えば行政への手続きではないのですが、これらの試験に合格するだけではその資格を活かして業務をすることはできず、行政書士または宅建士を登録するための指定書類の提出や登録費用の支払いが必要になります。
例えば以下のような書類が必要になります。
・登記されていないことの証明書(宅建のみ必要)
・身分証明書(宅建・行政書士両方で必要)
登記されていないことの証明書とは、申請者が成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するもので、法務局に行くと発行してもらえます。
身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証のような身分証明書と異なり、本籍の役所で発行してもらうものになります。
これらの申請は、一つ一つは難しくないものの、条件や提出先が微妙に異なり、書類が増えるほど混乱しやすくなります。

・登記されていないことの証明書は東京法務局への郵送か、地方法務局(本局)での申請が必要
→ 地元の支局では申請できない(長浜市の法務局ではなく大津市の法務局まで行く必要がある)
・登記されていないことの証明書には収入印紙、身分証明書には定額小為替が必要(どちらも手数料にあたるもの)
→ 収入印紙と定額小為替は郵便局内でも窓口が異なり、定額小為替は16時までしか購入できない
また、これとは別に「収入証紙」というものもあります。
・身分証明書は本籍の市町村役場に申請して郵送を依頼する(オンラインで申請できるところが多い)
これらの決まり事は基本的には法律に根拠があるので、手続きを間違えたり、受付時間を過ぎてしまった時に職員さんに「何とかしてよ」と言っても職員さんにも何とかする裁量はありません。
また、平日に働いている方は役所に足を運ぶこと自体が難しい状況も少なくありません。
こうした煩雑な手続きを代行するのが行政書士の主要業務の一つです。
AIと行政書士の未来

「行政書士はAIに仕事を奪われるのか?」という問いは、私が試験勉強をしていた頃からよく耳にしました。
開業後の実務経験からも思うのは、「技術的に実現可能であること」と「現実にその技術に取って代わられること」には相当な時間差があるということです。
自動車の自動運転を例に挙げると、技術的には実現可能でも、事故時の責任所在や保険、損害賠償といった法的枠組みの整備には時間がかかります。
行政手続きも同様で、各書類の管轄や必要な印紙・証紙などの要件は、法律の改正によって変わっていきます。
現在はe-Taxなど、確定申告をオンラインで行えるようになり、手続きの煩雑さは軽減した一面もあります。
ですが、毎年のように法改正される税制の専門家である税理士の仕事が無くなることはなく、それは行政書士においても同じことが言えるでしょう。
2026年の行政書士法の改正の影響

こちらの記事で詳しく解説していますが、2026年1月から行政書士法の一部が改正されます。
その中には「行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展に踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならない。」と士業法で初めて『デジタル社会の進展』という文言が明記されました。
これは、行政書士の仕事がAIによって淘汰されるのではなく、むしろAIやその他の新しい技術を積極的に活用し、情報通信技術(ICT)にも精通した存在を求められるという意図であると思います。
地域に根差した行政書士の価値
長浜市でクリエイター支援を専門とする行政書士として活動する中で、特に感じるのは「単なる書類作成や手続きの代行ではなく、人と人をつなぐ役割」の重要性です。
行政書士の仕事に将来性がないとする意見の理由として、「書類の作成」という言葉の響きが、事務的で誰にでも行える(単にプリンターで印刷するような)ものを連想し、それゆえにAIにも代替可能なのだという印象を持たれがちなのだと思います。
しかし、行政書士として依頼を受け書類を作成するという行為は、そのクライアントの意図を汲み取り、その問題や悩みの解決に繋げることに他ならないと考えています。
最近、当事務所にも相談を寄せられることが多い契約書の作成や補助金の申請書類の作成といった業務も、依頼者の挑戦や熱意を形にする、或いは将来的なトラブルをなるべく未然に防ぐといった「伴走型サポート」という側面が強いと感じています。
また、以前に私が懇意にしている理容店のご主人から、その常連のお客様を私が開いているスマホ教室へ紹介して頂いたこともあります。
そのお客様は私のスマホ教室も定期的に通って下さるようになり、「いつかは遺言書の作成をお願いしたい」とまで言って頂けるようになりました。
このような地域内の信頼関係と紹介の連鎖は、AIでは代替できない価値だと感じています。
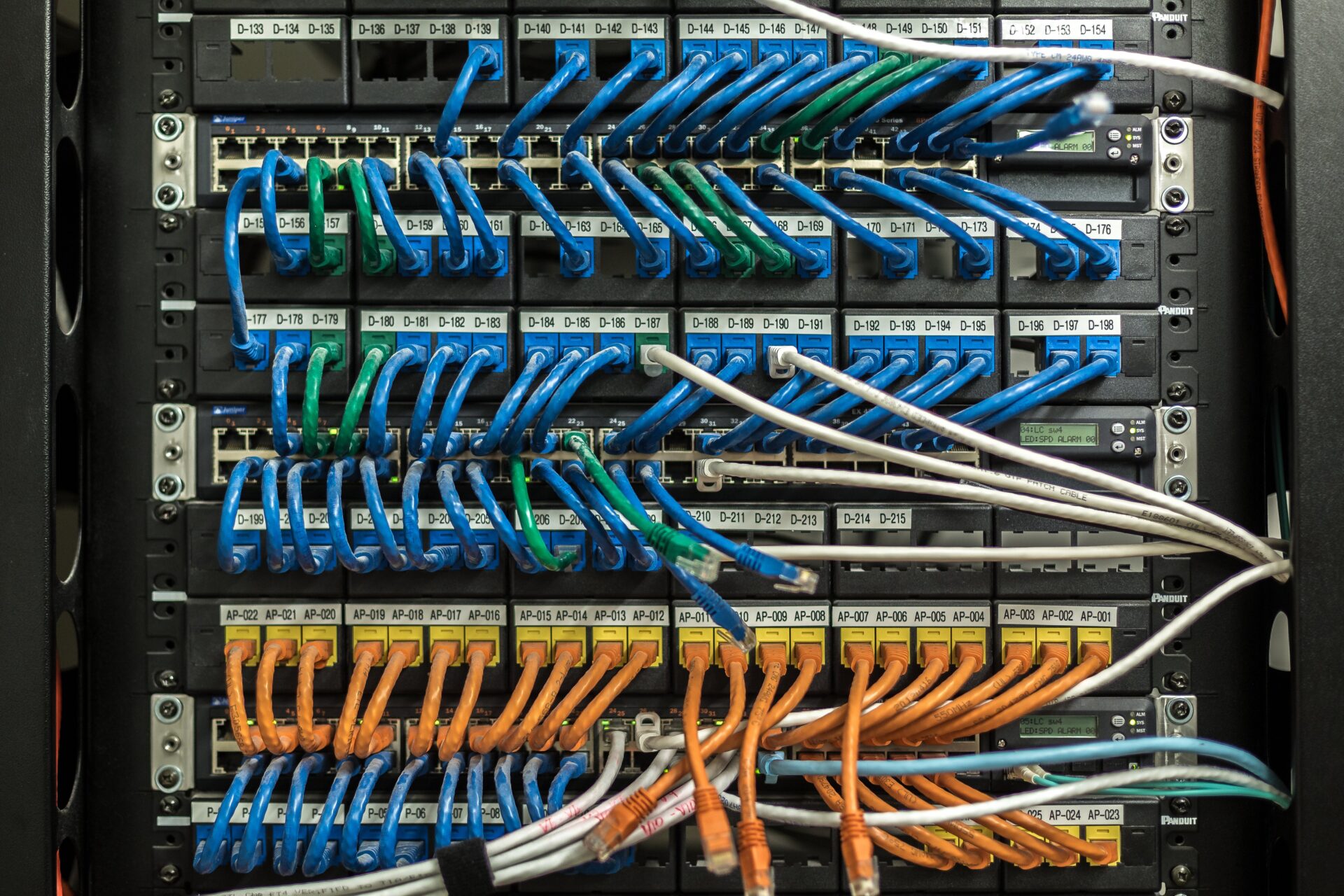
環境の変化を恐れず、活かす姿勢
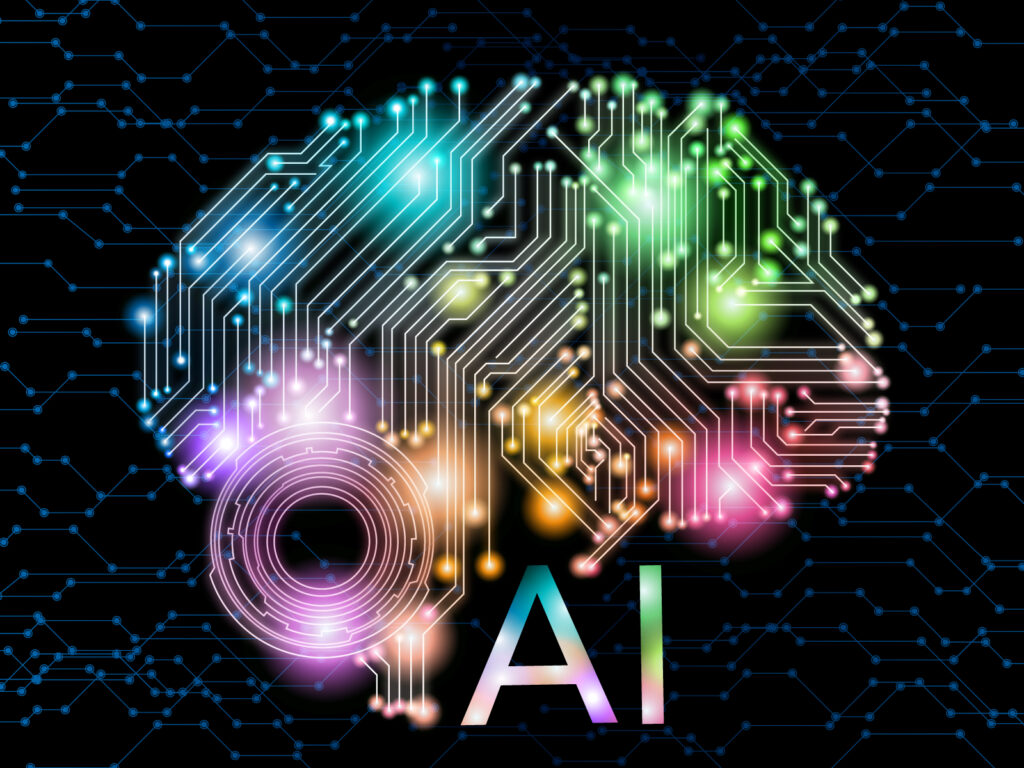
クリエイターとしての活動も続ける私自身は、新しい技術に触れることでワクワクするタイプです。
そのため、AIなどの新技術に「仕事を奪われる恐れ」よりも「どう使いこなすか」を考えるようにしています。
実際、私自身も色々な情報収集や分析にAIを活用しつつも、クライアントの真のニーズを理解し、地域特有の事情を踏まえた提案をするのは人間にしかできません。
長浜市という地方都市で行政書士として活動する中で、「人と人をつなぐ」「地域に根差した専門家」としての価値を高めることが、誰しもがAIを活用するようになる時代においても生き残っていける道であると確信しています。